茶の湯覚
このブログは、「茶道」についての月梅の個人的な覚書です。 調べたことを纏めると同時に、誰かのお役にたてれば幸いと思い、公開しています。
選択したカテゴリーの記事一覧
- « PREV
- | HOME |
- NEXT »
- 2025.12.16 [PR]
- 2011.03.01 【書籍】雨にもまけず粗茶一服
- 2011.01.20 【書籍】お茶席の冒険
- 2010.11.26 【書籍】茶の心 (淡交ムック)
- 2010.11.15 【書籍】お茶をはじめてみよう―ようこそ茶の湯の世界へ
- 2010.11.03 ちょっとお抹茶しませんか―ゆるゆるほっこり茶道生活
- 2010.11.02 茶会記の手引き―茶会をもっと身近なものに
- 2010.10.16 すぐわかる茶室の見かた
- 2010.10.15 京の茶の湯あそび (らくたび文庫)
- 2010.10.01 利休入門 (とんぼの本)
- 2010.09.10 見て・買って楽しむ茶器・陶芸の名品 (別冊炎芸術)
- 2010.06.22 茶の裂地名鑑
- 2010.06.16 くらべて覚える風炉の茶道具 炉の茶道具
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
茶道の関係する小説ということで読んでみました。大変楽しゅう読むことができました。
最初は登場人物の名前が似ているのでちょっと混乱したのですが、中盤からは、すごく個性的なキャラクターが魅力でした。
流派は創作だと思うのですが、茶の心や禅語、茶道具などがいやみでなく描かれていて、よかった。
映像化しても面白そう。
「友衛遊馬、18歳。弓道、剣道、茶道を伝える武家茶道坂東巴流の嫡男でありながら、「これからは自分らしく生きることにしたんだ。黒々した髪七三に分けてあんこ喰っててもしょうがないだろ」と捨て台詞を残して出奔。向かった先は、大嫌いなはずの茶道の本場、京都だった―。個性豊かな茶人たちにやりこめられつつ成長する主人公を描く、青春エンターテイメント」
続編の「風にもまけず粗茶一服」も発売中のよう。併せて読みたい。
しかし、続編とは思えないほど、カバーの雰囲気が違う。
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
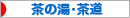
にほんブログ村
最初は登場人物の名前が似ているのでちょっと混乱したのですが、中盤からは、すごく個性的なキャラクターが魅力でした。
流派は創作だと思うのですが、茶の心や禅語、茶道具などがいやみでなく描かれていて、よかった。
映像化しても面白そう。
「友衛遊馬、18歳。弓道、剣道、茶道を伝える武家茶道坂東巴流の嫡男でありながら、「これからは自分らしく生きることにしたんだ。黒々した髪七三に分けてあんこ喰っててもしょうがないだろ」と捨て台詞を残して出奔。向かった先は、大嫌いなはずの茶道の本場、京都だった―。個性豊かな茶人たちにやりこめられつつ成長する主人公を描く、青春エンターテイメント」
続編の「風にもまけず粗茶一服」も発売中のよう。併せて読みたい。
しかし、続編とは思えないほど、カバーの雰囲気が違う。
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
にほんブログ村
PR
お茶のお稽古に通う著者のエッセイ。流派は藪内流なのでちょっとめずらしい。体験談・感想メインの内容なので、これを読んで、知識が増えるということは、あまりありません。(へぇと思うことはありますが。)あくまでも読み物ですが、読みやすい文章でした。
「お茶の教室は未知の世界への扉。よけいなものが削ぎ落とされて、静かに何かが深まっていく―。知らない世界を探検して得る「和」の楽しみ方。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
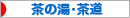
にほんブログ村
「お茶の教室は未知の世界への扉。よけいなものが削ぎ落とされて、静かに何かが深まっていく―。知らない世界を探検して得る「和」の楽しみ方。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
にほんブログ村
大型本で、写真集のようでした。写真がきれい。
裏千家家元の言葉が書かれているのですが、平易な文章のようで、奥が深い。きっと、どれだけ茶道と関わっているかで、読み取れるものが違うのではないでしょうか。
もっと習練したら、もう一度読みたい。
「鵬雲斎家元の平易な文章に、納屋宗淡が的確丁寧に解説。写真家井上隆雄が細見美術館などの名品を贅沢に撮影し、茶の心の深奥を見事に表現。裏千家茶道海外布教50周年記念出版。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
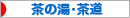
にほんブログ村
裏千家家元の言葉が書かれているのですが、平易な文章のようで、奥が深い。きっと、どれだけ茶道と関わっているかで、読み取れるものが違うのではないでしょうか。
もっと習練したら、もう一度読みたい。
「鵬雲斎家元の平易な文章に、納屋宗淡が的確丁寧に解説。写真家井上隆雄が細見美術館などの名品を贅沢に撮影し、茶の心の深奥を見事に表現。裏千家茶道海外布教50周年記念出版。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
にほんブログ村
お茶を始めるメリット、茶道のお稽古のはじめ方、はじめてからのアドバイスなどがわかりやすく書かれています。とくに、お稽古のはじめ方(教室の探し方や、用意するお道具、心得など)について書かれている本は少ないので、貴重ではないでしょうか。
とくに、「ルポ・初めてのお稽古日」はお稽古の勝手のわからない人には、イメージがしやすくなっていいのでは。まぁ、教室によって、お稽古の雰囲気は異なると思いますが。
茶道をはじめたいけど、どうすれば・・・という方は一読してもいいと思います。
※裏千家です。
「茶道には日本の文化が詰まっています。着物、作法、和菓子、料理、伝統工芸の道具、そして季節を大切に思う心。もう一度自分を見つめなおしてみませんか。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
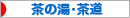
にほんブログ村
とくに、「ルポ・初めてのお稽古日」はお稽古の勝手のわからない人には、イメージがしやすくなっていいのでは。まぁ、教室によって、お稽古の雰囲気は異なると思いますが。
茶道をはじめたいけど、どうすれば・・・という方は一読してもいいと思います。
※裏千家です。
「茶道には日本の文化が詰まっています。着物、作法、和菓子、料理、伝統工芸の道具、そして季節を大切に思う心。もう一度自分を見つめなおしてみませんか。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
にほんブログ村
ほんわかイラストレーターによる茶道体験エッセイ。
難しい用語などはほとんどなく、茶道のおけいことそれにまつわる楽しみを、やわらかいイラストとともに書かれています。
読みやすいので、これから茶道を始めたいと思っている方におススメするのにいいかなぁと思います。
※裏千家です。
「慣れないお稽古に四苦八苦するものの、茶道をかじって見えてきた和の暮らしの楽しみ方。おいしいもの・うつくしいもの、色づく歴史、季節の移ろい、おもてなしの心。かわいいイラストも満載。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
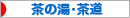
にほんブログ村
難しい用語などはほとんどなく、茶道のおけいことそれにまつわる楽しみを、やわらかいイラストとともに書かれています。
読みやすいので、これから茶道を始めたいと思っている方におススメするのにいいかなぁと思います。
※裏千家です。
「慣れないお稽古に四苦八苦するものの、茶道をかじって見えてきた和の暮らしの楽しみ方。おいしいもの・うつくしいもの、色づく歴史、季節の移ろい、おもてなしの心。かわいいイラストも満載。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
にほんブログ村
茶会記についての入門書。茶会記との触れあい方をエピソードを挟みながら記述されています。
茶会記の作り方について。茶会のストーリーを作るというのは大変興味深かった。実際の茶会を作ることはなかなか実現できることではないけれど、物語を考えながら、道具組を考え、茶会記を作ってみるのも楽しいかもしれません。
古会記の読み方もいくつか紹介されていました。江戸時代の文献は難しいですが、当時の茶人を思い浮かべて読んでみるのもよいものですね。
茶会記にまつわる語録や便利表も付いています。
「茶会の台本、茶会の記録として、大切な役割をもつ茶会記。先人の記した宝に学び、現代の茶会記を知り、茶会記を正しく記せるように...。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
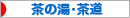
にほんブログ村
茶会記の作り方について。茶会のストーリーを作るというのは大変興味深かった。実際の茶会を作ることはなかなか実現できることではないけれど、物語を考えながら、道具組を考え、茶会記を作ってみるのも楽しいかもしれません。
古会記の読み方もいくつか紹介されていました。江戸時代の文献は難しいですが、当時の茶人を思い浮かべて読んでみるのもよいものですね。
茶会記にまつわる語録や便利表も付いています。
「茶会の台本、茶会の記録として、大切な役割をもつ茶会記。先人の記した宝に学び、現代の茶会記を知り、茶会記を正しく記せるように...。」
■―■―■―■―■―■―■―■―■
茶道に関するブログを探すなら↓↓
にほんブログ村
「■既刊『茶室のみかた図典』を整理して、見やすくなるよう大幅にリニューアル。茶室の基本的な見かた・用語がこの1冊でわかる。
■妙喜庵待庵、如庵、高台寺傘亭・時雨亭をはじめ有名な茶室40席の見どころ・構成・由緒を写真・イラスト・平面図付きで解説。
■茶席・窓・建具・露地・手水鉢・灯籠などの分野別に、茶室に関する352項目の用語をイラストを交え丁寧に図解。
■「茶室は、ただ単に見るだけのものではありません。身体でもって体験するものです。」(「はじめに」より)茶室を体験し・楽しむための手引となる入門書。」
著名な茶室の紹介(茶室探訪)と茶室用語図典からなる。
茶室探訪は見所や図面が載っている。関連する用語や人物のトピックがあって読みやすい。が、写真が少ない。
茶室用語図典は項目別に細かく載っている。図が載っているのは分かりやすくて良いと思う。
■妙喜庵待庵、如庵、高台寺傘亭・時雨亭をはじめ有名な茶室40席の見どころ・構成・由緒を写真・イラスト・平面図付きで解説。
■茶席・窓・建具・露地・手水鉢・灯籠などの分野別に、茶室に関する352項目の用語をイラストを交え丁寧に図解。
■「茶室は、ただ単に見るだけのものではありません。身体でもって体験するものです。」(「はじめに」より)茶室を体験し・楽しむための手引となる入門書。」
著名な茶室の紹介(茶室探訪)と茶室用語図典からなる。
茶室探訪は見所や図面が載っている。関連する用語や人物のトピックがあって読みやすい。が、写真が少ない。
茶室用語図典は項目別に細かく載っている。図が載っているのは分かりやすくて良いと思う。
イラストが可愛かったり、構成も入門前の方には楽しめるものです。茶道を知っている方なら、当たり前のことばかりかもしれませんが・・・京都でやっているお茶会の情報も載っていますので、「京都で茶道を・・・」と思う方は、一つかばんに忍ばせておいてもよろしいかと思います。お値段も、重さもお手軽です。
利休の人となりに迫った一冊。
「いったい、この人の何が「凄い」のでしょう?
利休の逸話は数多いですが、そのほとんどが作り話です。
信長、秀吉とのほんとうの関係、楽茶碗にこめられた意味、暗い茶室でこころみた工夫―いま注目の若手茶人が、茶碗、茶室、侘び、禅、死ほか一〇章で語る、茶の湯をよく知らない人のための新・利休入門。」
茶人の中で神格化されている利休をどちらかというと、人としてとらえています。
わびさびなどの茶道の精神の説明はあまりない。
お稽古・手前の解説書でもないので、ちょっと茶道・利休に興味がある人にお勧め。
写真はオールカラーでした。
「いったい、この人の何が「凄い」のでしょう?
利休の逸話は数多いですが、そのほとんどが作り話です。
信長、秀吉とのほんとうの関係、楽茶碗にこめられた意味、暗い茶室でこころみた工夫―いま注目の若手茶人が、茶碗、茶室、侘び、禅、死ほか一〇章で語る、茶の湯をよく知らない人のための新・利休入門。」
茶人の中で神格化されている利休をどちらかというと、人としてとらえています。
わびさびなどの茶道の精神の説明はあまりない。
お稽古・手前の解説書でもないので、ちょっと茶道・利休に興味がある人にお勧め。
写真はオールカラーでした。
茶道具展覧会の図録のような感じの一冊。
近現代の作家の作品がカラーで楽しめる。
ギャラリーも載っているので、購入することも可能。
(おいそれと手が出る価格じゃないですが)
出版社: 阿部出版 (2010/02)
ISBN-10: 4872422171
近現代の作家の作品がカラーで楽しめる。
ギャラリーも載っているので、購入することも可能。
(おいそれと手が出る価格じゃないですが)
出版社: 阿部出版 (2010/02)
ISBN-10: 4872422171
茶の湯の場で用いられている裂地(きれじ)について、800点余りをカラーで収録し、図鑑風に紹介する。
地色、文様、織り方についての基礎知識、様々なキーワードから名称を探せる索引付。
ハードカバーで大きいサイズの本なので、持ち運びはできませんが、一つ一つの裂地について、詳しい解説が付いているので、辞典として手元に置きたい一冊。
出版社: 淡交社 (2001/07)
ISBN-10: 4473018164
地色、文様、織り方についての基礎知識、様々なキーワードから名称を探せる索引付。
ハードカバーで大きいサイズの本なので、持ち運びはできませんが、一つ一つの裂地について、詳しい解説が付いているので、辞典として手元に置きたい一冊。
出版社: 淡交社 (2001/07)
ISBN-10: 4473018164
「本書は、茶道初心者のために、またお稽古の予習・復習のために、心強いテキストとなる一冊です。
風炉と炉それぞれのお道具のちがい、点前中のあつかいなど、たいせつなポイントがすぐ解ります。
お茶のお稽古の予習・復習のために、風炉と炉の道具の違い、あつかいの違いを、比較対照方式で解説。
入門してまもない人、茶の湯覚えを確認したい人に便利な一冊。 」
写真が多く、雑誌みたいなつくりなので、眺めているだけでも楽しいし、勉強になります。
単行本: 101ページ
出版社: 淡交社 (2006/03)
ISBN-13: 978-4473033031
発売日: 2006/03
風炉と炉それぞれのお道具のちがい、点前中のあつかいなど、たいせつなポイントがすぐ解ります。
お茶のお稽古の予習・復習のために、風炉と炉の道具の違い、あつかいの違いを、比較対照方式で解説。
入門してまもない人、茶の湯覚えを確認したい人に便利な一冊。 」
写真が多く、雑誌みたいなつくりなので、眺めているだけでも楽しいし、勉強になります。
単行本: 101ページ
出版社: 淡交社 (2006/03)
ISBN-13: 978-4473033031
発売日: 2006/03
茶の湯@wiki
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| HOME |


